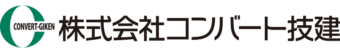「ダブルPC工法」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
ちょっと聞きなれない響きかもしれません。でも、私たちが日々見上げる団地や、昔ながらの集合住宅の多くに、この技術が使われているのです。
時代をさかのぼれば、戦後の日本。
住宅が圧倒的に足りず、人々は安心して住める場所を求めていました。そんななか、国と民間が一緒になって「早く、そして丈夫な家を建てよう」と立ち上がったのが、この工法のはじまりです。住宅公団(現在のUR)などが中心となり、新しい時代の家づくりが始まりました。

ダブルPC工法の「PC」は、「プレキャスト・コンクリート(Precast Concrete)」の頭文字。
簡単に言えば、コンクリートの壁(Wall)をあらかじめ工場でつくっておいて、それを現場に運んで、組み立てるというやり方です。
まるで積み木を組み合わせるように、すばやく、正確に、そして丈夫に。
この工法のすごいところは、その耐久性。
昭和30年代に建てられた建物が、今もなお健在。中には、「まだ数十年は現役」と言われるものもあるのです。50年、60年という時間を越えて、私たちの暮らしを支え続けている。それだけで十分に価値があると言えるでしょう。
もちろん、団地のように老朽化が進んでいる建物もあります。
けれど、その中でも「まだまだいける」と評価されているのが、ダブルPC工法でつくられた建物たちなのです。
時代は変わり、家の形も変わってきました。
けれど、「長く住める」「安心して暮らせる」という願いは、いつの時代も変わらない。
ダブルPC工法は、そんな思いをかたちにした、日本の住宅づくりのひとつの知恵と言えるかもしれません。
何気なく通り過ぎる古い建物にも、実はこんな物語が隠れているのです。
このダブルPC工法には、まだまだ良いところがたくさんありますが、今回はまずその歴史と基本的な仕組みをご紹介しました。